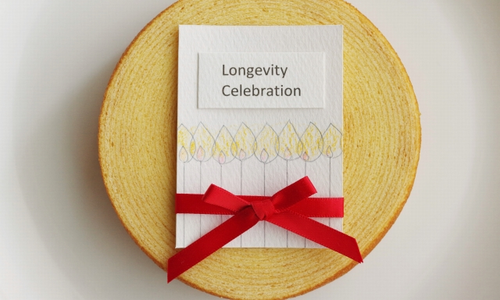
敬老の日お祝い いつから・何歳からが一般的?孫が祝うもの?
2017/08/15
9月の第三月曜日は敬老の日。
でも「敬老の日っていつから?何歳から!?」というのはとっても疑問です。
孫から祖父母へ?自分の親なら何歳から?
気になるポイントをまとめました。
敬老の日 いつから祝ってあげるもの?
「お年寄りがいたら席を譲らなきゃ」
と、自分では思いますが、
「電車で席を譲られちゃった…」
と、一方で両親は老人と見られたことがショック。
この状況、家族内でも結構あるのではないでしょうか。
敬老の日も、これと似たような感じです。
60代、70代でも現役バリバリの人もいれば、
大きな病気をすれば50代でもぐっと老け込みます。
ここからが老人、という年齢の線引きがないので、
お互いの認識に差があるんですね。
というわけで、
敬老の日に「敬老」されるのは何歳から?
お年寄りは何歳から?
という疑問を見て行きましょう。
何歳から「お年寄り」に?
実際のところ、
「敬老の日のお祝い対象は〇歳から」
という決まりはありません。
全国の各自治体でも「敬老祝い金」などの名目で
お年寄りにお金を支給する制度がありますが、
対象年齢や金額などは様々。
何歳からと判断するのは難しいのです。
ですが、
敬老の日の制定由来を見てみると、起源は兵庫県にあり、
◆年寄りを大切に
◆年寄りの知恵を活用しよう
などの趣旨で提唱されたものとされています。
ここから読み取れる「年寄り」や「老人」というのは
年老いて現役や第一線を退いたけれど、沢山の知恵や経験を持っている人たち
というニュアンスではないでしょうか。
そう考えると、
仕事を退職した人というのがまず第一関門になりそうですね。
年齢的な区分
人口統計の区分では、
- 64歳以下…現役世代
- 65~74歳…前期高齢者
- 75歳~…後期高齢者
というふうに分類されています。
つまり、
64歳までは敬老の日の対象外と考えてよさそうです。
65歳以上になったら、若々しくても高齢者入り。
年金生活に入っている人なら、お祝いしてもいいかもしれません。
さすがに75歳、後期高齢者になったら、
敬老されて不満な人はあまりいないかと思います。
敬老の日調査 何歳からお年寄りと見られる?
さて、ある市場調査によると、高齢者をイメージする年齢は
70歳~
という回答が最も多いようです。
次いで65歳~。
つまり、
どんなに頑張っても70歳を過ぎると老人として認識されてしまうのですね。
また、老けて見えるポイントは、
体形(背中や腰、膝の曲がり具合)や姿勢
なのだそうです。
やはり腰が曲がったり杖をついたりしていると、
お年寄りというイメージになるのですね。
ちなみに、若い世代ほど
「敬老の日を祝いたい・自分だったら祝ってほしい」
と感じるようですが、高齢者の年齢に近づくほど、
祝われたくない(つまり加齢を認めたくない)ようです。
60代で、身体がしゃんとしている方ならば、
敬老の日のお祝いはもう少し先送りしてあげるのが
心遣いかもしれませんね。
敬老の日は何歳から 孫の有無も関係
もう一つ、敬老の日と言えば
孫の有無というのも大きいのではないでしょうか。
もちろん、誰から誰を祝う(敬う)ものという決まりはないですが、
まだまだ元気で老人扱いされるのは嫌という人でも、
「おじいちゃん・おばあちゃんへ」と孫に祝われるのは
まんざらでもない、ということも多いもの。
50代でも60代前半でも、孫から見たら
「おじいちゃん・おばあちゃん」ですからね。
子供が祝おうとすると「まだ老人じゃないから!」
と拒否されそうでも、孫なら年齢を気にせずお祝いできます。
というわけで、
孫からの気持ちを、親(お年寄りの子供に当たる世代)が手助けしてお祝いする
というスタンスが、一番角がたたないのかもしれません。
それでも
◆普段お世話になっているお礼が言いたい
◆何かしてあげたい
と言う場合は、それぞれの誕生日や父の日・母の日に
しっかりお祝いをしてあげるのがいいかと思います。
まとめ
敬老の日は何歳からお祝いするか?
ということについては、
相手が喜んでくれるかどうかに尽きると思いますが、
まだ仕事をしている60代の人
というのは、喜んでもらえない可能性が高いですね。
孫がいれば孫経由で、そうでなければ70歳以上、
というところが、一般の感覚に近いかもしれません。